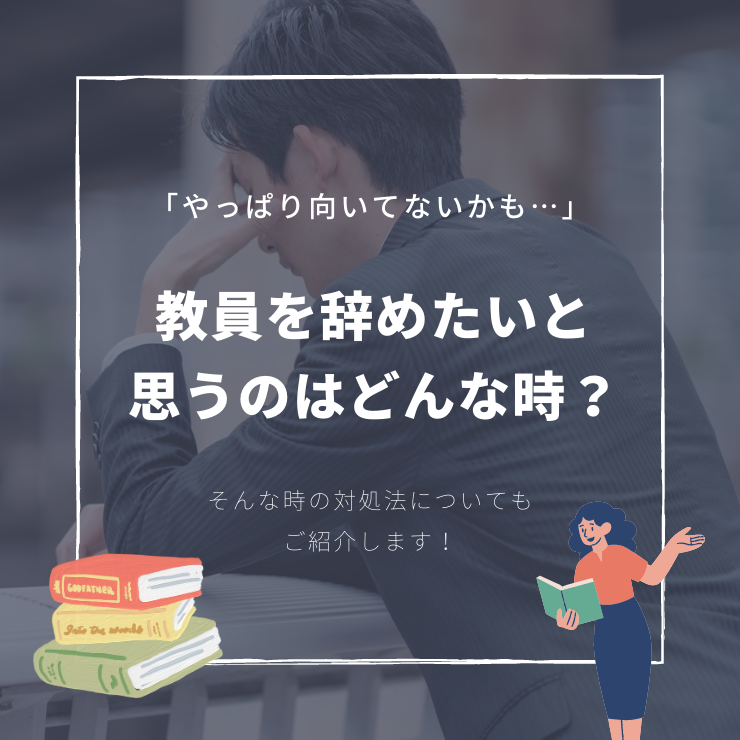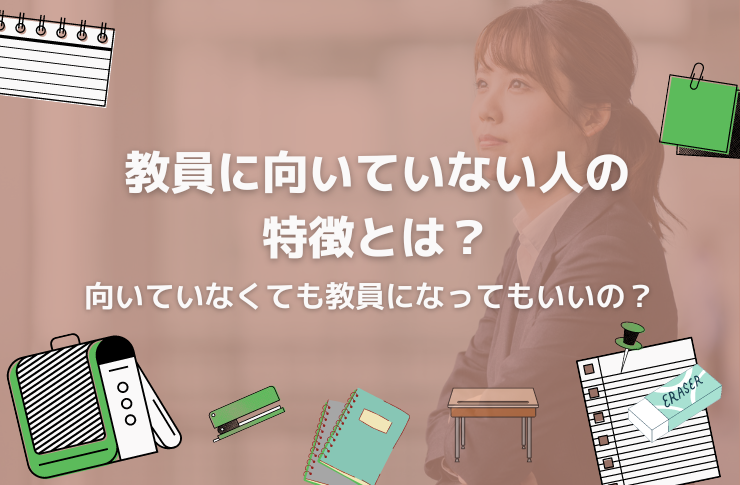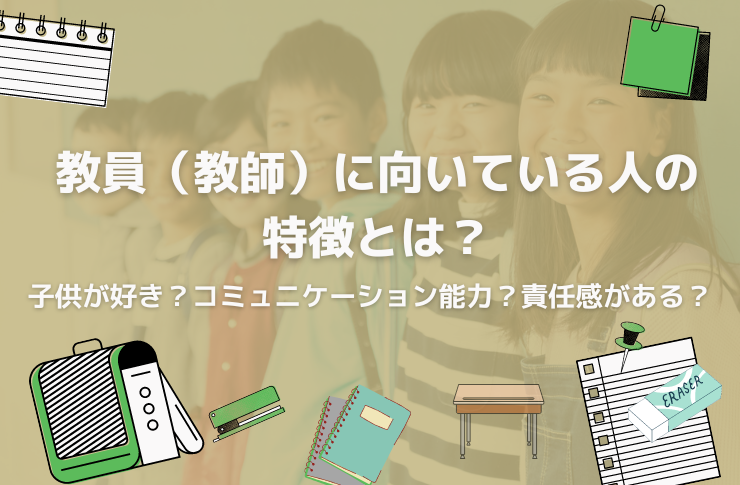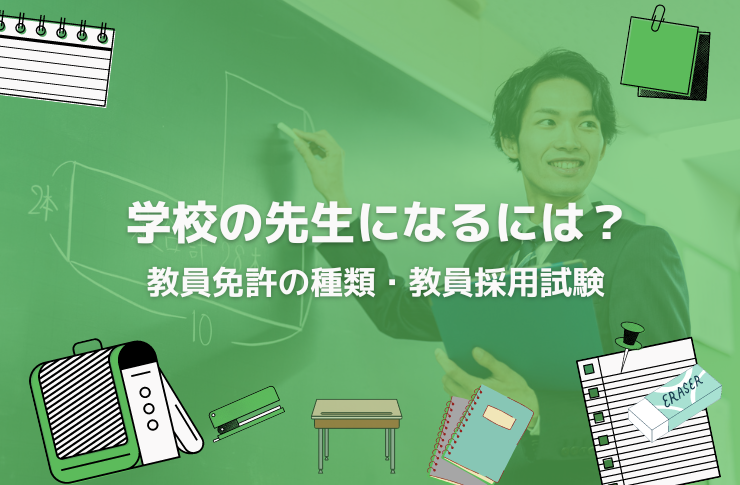
子どもたちの成長をサポートする教員は、子供の『将来に就きたい職業ランキング』で上位常連のお仕事です。
一般的に教員になる方法は「大学に行って教員免許を取得する」というなんとなくのイメージがありますが、それ以外にも教員として働くことができます。
この記事では、教員になる方法や教員免許の種類などについてご紹介します。
また、こちらの記事で教員のすべてについて紹介していますので、併せてご覧ください。
▷教員の『なり方』から『辞め方・転職先』まで『すべて』をご紹介!|向き不向き、向いていない(辞めたい)際の対処法なども多角的にご紹介
教員とは
教員とは、一般的に「学校の先生」と呼ばれるように、小学校~高校などの学校の先生です。子供たち(生徒たち)の心身の成長を『授業』『生活指導』などで全面的にサポートします。学校の種類によってサポート内容は異なり、年齢に合った指導を行います。
教員の仕事内容についてはこちらにまとめていますので、是非ご覧ください。
▷教員(学校の先生)ってどんなお仕事?|教員の仕事内容や役割・業務内容についてご紹介!
教員になるための大まかな流れ
学校の先生(教員)になるには、『教員免許を取得し教員採用試験に合格』することが一般的です。『教員免許』は、大学や短大で教職課程(教育実習(現場実習)を含む)を履修し、取得する方法が広く知られていますが、教職課程を修了していない人でも免許取得が可能です。
教員免許を取得後に公立の学校であれば『各都道府県や自治体が主催する採用試験』、私立の学校であれば『各学校で行われる採用試験』を受験し、合格し採用される必要があります。
『教員免許』『教員採用試験』については、これから詳しくご紹介します。
こちらもチェック
▷教員(教員)に向いている人の特徴とは?|子供が好き?コミュニケーション能力?責任感がある?
▷教員に向いていない人の特徴とは?|向いていなくても教員になってもいいの?

教員免許とは
教員になるために必要な教員免許は、教員職員免許法に基づいた『国家資格』です。学校の種類や担当教科に適した教員免許を取得する必要があります。
また、教員免許は「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」の3種類あります。
※ 2022年4月現在有効期限は10年間ですが、教員免許更新制を廃止する流れとなっています。
普通免許状について
教員免許の代表格として挙げられるのが『普通免許状』です。教員養成課程のある大学(または短大)で必要な単位を取得・卒業し、各自治体の教育委員会に授与申請することで、免許を取得できます。
普通免許状はすべての都道府県で有効なので、どこの都道府県でも教員になれます。
特別免許状について
大学などで教職課程を履修しなくても、特定の分野において知識や経験を持つ人が取得できる免許が『特別免許状』です。優れた知識・経験を有する社会人を学校現場へ迎え入れるために授与されます。
特別免許上を授与されれば、普通免許を持っていなくても学校の先生として教育に携われます。特別免許状の授与を受けるには、任用しようとする者(教育委員会や学校法人など)の推薦、各自治体の教育委員会が行う教職員検定に合格することが必要です。
学校の種類・教科ごとに特別免許状があります。
※ 特別免許状には、幼稚園教諭・養護教諭栄養教諭にはありません。
臨時免許状について
教育委員会や学校法人などの任用者または雇用者が、普通免許状を有するものを採用できない場合に、例外的に授与される免許が『臨時免許状』です。
取得するには、各自治体が行う教育職員検定に合格する必要があります。
※ 栄養教諭には臨時免許はありません。

校種による必要な教員免許の違い
教える学校や教科によって、必要な教員免許が異なります。
・幼稚園教諭免許状
幼稚園の先生になるための資格
・小学校教諭免許状
小学校教師になるための資格
・中学校教諭免許状 ※
中学校教師になるための資格
・高等学校免許状 ※
高等学校教師になるための資格
・特別支援学校教諭免許状
障害のある児童・生徒が通う特別支援学校の教師になるため資格
・養護教諭免許状
保健室の先生(養護教諭)になるための資格
・栄養教諭免許状
学校給食の献立を考えることや、食育などの授業を行う
※ 注意
中学校教師、高校教師は専門教科の授業を行うため「中学校教諭一種免許状 数学」など、教科ごとに教員免許状があります。また、高等学校教諭には二種免許状はありません。
教員免許取得方法について
ここから教員免許の取得方法について、下記の2パターンご紹介します。

①必要な単位を取得する
先述しましたが、普通免許の取得方法は、教員養成課程(教職課程)のある大学(または短大)で必要な単位を取得・卒業し、各自治体の教育委員会に授与申請することで、免許を取得できます。
※ 大学によって取れる免許(科目など)が限られています。
【普通免許の種類】
普通免許の種類は「専修免許状」「一種免許状」「二種免許状」があり、単位などにより授与される免許種類が分かれます。
・ 一種免許状(4年制大学卒業程度)
4年制大学で、所定の科目を取得(教科・教職科目など合計67単位)し卒業することで取得できる
・二種免許状(短大卒業程度)
主に短期大学、所定の科目を取得(教科・教職科目など合計45単位)し卒業することで取得できる
・専修免許状(大学院修士課程修了程度)
一種免許状を有する(または要件を満たす)者が修士号等の基礎資格を得るとともに、大学院または、四年制大学専攻の課程で24単位以上を取得し卒業することで取得できる。
通信大学で単位を取得
「通信大学」で教員免許をとる方法もあります。通信大学で必要な科目を履修し卒業することで教員免許を取得することができます。
社会人で教員免許を取得目指す方は「通信大学」で取得する方が多く、一般的な4年制大学を卒業した方は2年ほどで取得できます。
科目履修生
大学を卒業している人は、科目履修生として特定の科目だけ履修することで教員免許を取得することができます。
②教員資格認定試験に合格する
大学などに通うことなく、教員免許を取得する方法があります。
「幼稚園教員」「小学校教員」「特別支援学校教員」であれば『教員資格認定試験』に合格することで教員免許を取得できます。教員資格認定試験での免許状は「二種免許状」です。
文部科学省のホームページに、下記のように記載されています。
“広く一般社会に人材を求め、教員の確保を図るため、大学等における通常の教員養成のコースを歩んできたか否かを問わず、教員として必要な資質、能力を有すると認められた者に教員への道を開くために文部科学省が開催している試験です。”
(文部科学省-教員資格認定試験)
【教員資格認定試験の種類・受験資格】
・幼稚園教員資格認定試験
高校卒業し、20歳以上で保育士として3年以上の実務経験がある人
・小学校教員資格認定試験
高校卒業し、20歳以上の方
・特別支援学校教員資格認定試験
22歳以上で、大学を卒業または文部科学大臣が指定する教育養成機関や高校を卒業した方

教員免許を取得した後は?
公立の学校先生になる場合
公立の学校で働く際は、教員免許を取得後に教員採用試験を受け、合格することで教員として採用されます(教員になることができます)。
【教員採用試験】
教員採用試験は「公立学校教員採用選考試験」の略です。
採用試験の内容は自治体によって異なりますが、一般的に「筆記試験」「面接試験」「実技試験」「適正検査」が行われます。
・筆記試験
一般教養、教職教養、専門教養、小論文
・面接試験
個人面接、集団面接、ディベート(討論)、模擬授業
・実技試験
小学校教員や、中・高校の美術、音楽などの副教科と、英語教科の受験者は実技試験が行われることがあります。
・適性検査
一部の自治体では、SPI試験などが行われることがあります。
【教員採用試験のスケジュール】
教員採用試験は毎年実施されており、教員採用試験のスケジュールは各自治体によって異なります。
一般的に募集要項配布が『3月下旬〜5月下旬頃』が多く、その後に願書提出し、一次試験が『6月〜7月』、二次試験が『8月〜9月』に頃に実施されます。
二次試験の合否は8月下旬から遅くとも10月中旬までに発表されます。合格者は採用候補者名簿に登録され、その後説明会、面接後に3月中旬頃までには赴任校が決定します。
【倍率】
文部科学省「令和3年度(令和2年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント」によると
・小学校の採用倍率 :2.6倍
・中学校の採用倍率 :4.4倍
・高等学校の採用倍率:6.6倍
近年、採用倍率は減少傾向にあります。
【受験資格】
教員採用試験の受験資格は「普通免許」保持者ですので、特別免許状は対象となりません。
※ 基本的に受験資格は「普通免許資格」保持者ですが、一部自治体では年齢制限(40〜50歳など)を設けている場合もあるため、受験の際は確認が必要です。
【教員採用試験での教員免許一種・二種での違い】
一種・二種での教員採用試験の扱いの差はなく、あくまでも試験の成績によって採用されます。
また、二種免許で教師として働いている人は教員職員免許法の中で「一種免許状への切り替え努力義務」が定められています。一種への切り替えは、在職年数による単位取得によって切り替えられることができます。
私立の学校先生になる場合
私立学校での教員を目指す場合は、公立の教員採用試験を受ける必要はありません。私立の学校教員は、自治体で雇用されるわけではなく、学校法人で雇用されます。
そのため、採用スケジュールは学校によって様々であり、基本的に欠員補充の募集が多いため毎年採用をしているわけではありません。

講師として教員になる
教員採用試験に合格せずとも「講師」として働くことができます。講師になるためには、教育委員会に登録を行い、紹介や声がかかることで「講師」として働くことができます。
講師登録をするためには、教員免許を持っていることが基本的に前提となっています。
まとめ
この記事では、教員になるための方法についてご紹介しました。
大学で教職課程を取っていなくも、新たに単位を取得することや、試験を受験することで教員になることができます。これからの未来、活躍する子供(生徒)を支える教員です。
興味がある方は挑戦してみてはいかがでしょうか?